
移動薬局(モバイルファーマシー)って、何ですか?
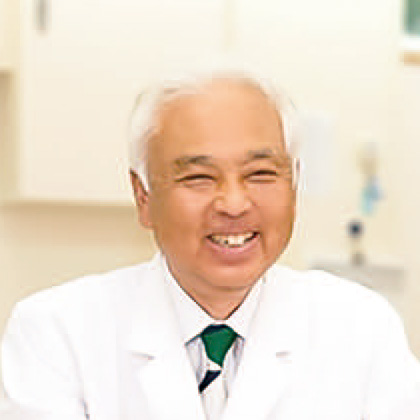
村木
災害時に調剤や医薬品を供給できる車両です。全国での導入台数は、薬剤師会導入が13台、大学支援での導入が5台、当薬局のケースのように民間企業による導入が2台あります。災害は減ること無く、全国レベルで発生しています。避難される方にとって、医薬品の安定した供給は薬剤師の使命と考え、地域薬局としてアイ薬局が2018年に購入しました。


西日本豪雨では、倉敷市真備町の1/3が浸水するという大災害が発生しました。早速、この移動薬局を派遣されました。当時の様子をお聞かせください。
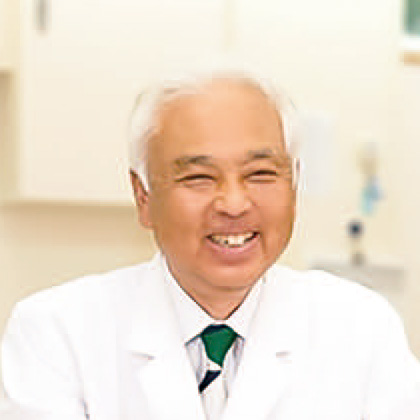
村木
2018年6月28日から7月8日まで降り続いた雨で7月7日から8日にかけて倉敷市真備町の小田川が決壊しました。早速、最大の避難所であった岡田小学校に出動しました。
炎天下で汗の絶えない毎日でしたが、7月11日より21日まで設置して医療用医薬品および一般医薬品(OTC) を供給することが出来ました。
避難所における移動薬局では、どのような経験をされましたか。
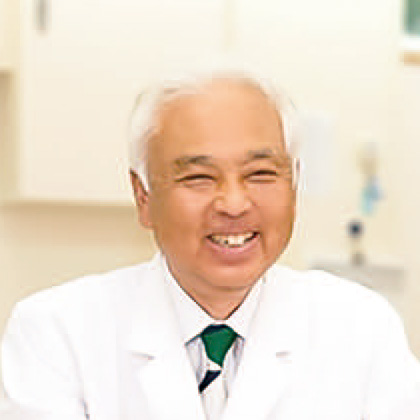
村木
日頃から服用されているお薬を中断することなくお渡しできたこと、街中に積もった土砂がホコリとして舞い上がり目の痛みを訴えておられる多くの方への対応などあらゆる医療ニーズにお応えできたのではないかと思います。最も印象に残っていることは、被災に遭われた皆様の悲しい生活の現実を伺うことでした。また、日赤医療チームや国境を越え医療支援を行っている特定非営利活動法人TMAT のドクターが移動薬局に大変ご興味を持たれ、薬が届いたと歓喜されていたのが印象的でした。
モバイルファーマシーの維持管理は結構大きな負担になると聞きましたが。
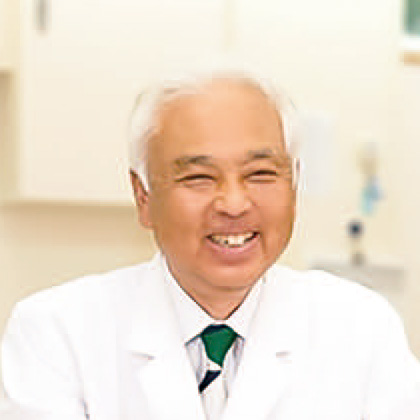
村木
確かに購入時より維持管理は大きな課題です。そこで平時でも地域で役立てるため、地域の健康管理に移動薬局の力を発揮させることにしました。血圧計、骨密度計あるいは血糖値測定機器などを山間部の池田地区に運搬して、測定に参加していただくと同時に健康教室を開いております。
健康教室の様子を教えてください。
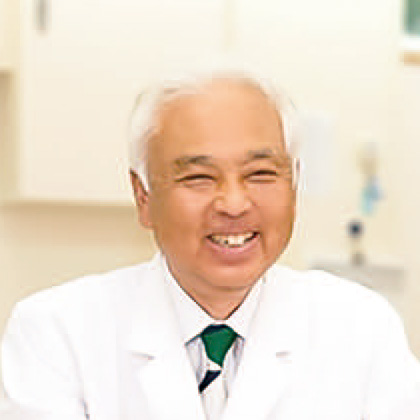
村木
2024年8月より、「池田地区健康教室」として月に1回開講しています。地元の池田小道の駅(いけだ こみちのえき)のスタッフの方の協力を得ながら、地域の高齢者が毎回10~20名参加されます。講師には、岡山大学大学院医歯薬研究科の寄付講座(アイ薬局が開設)より教員や学生が応援に参加されます。

健康教室のテーマはどのようなお話しですか?
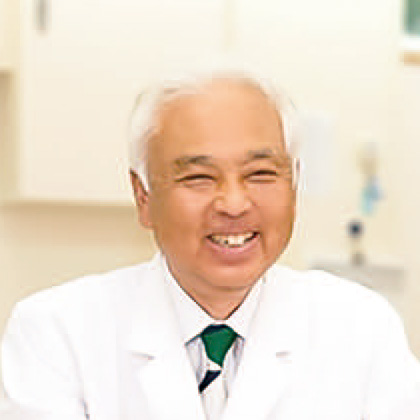
村木
熱中症対策、梅雨時期の不調、高齢者の不眠、高齢者のうつ、便秘、フレイル、高血圧などです。
薬局として、地域住民の健康管理を目的に発展することは住民の皆さまにとって有り難いことと思います。皆さんの声や今後の展開についてお聞かせください。
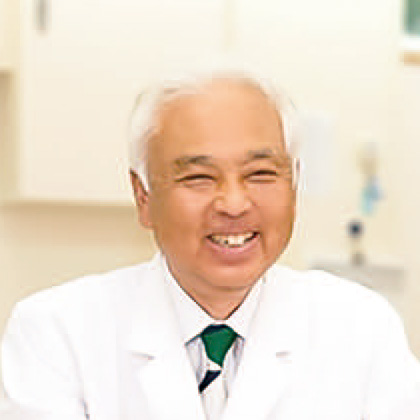
村木
参加者の皆様からは、「病気や薬について様々なお話が聞けて勉強になる」、「計測コーナーのおかげで通院の間の健康チェックになり健康管理に前向きになりました」とご好評をいただいております。これからも継続してほしいというお声もいただいており、今後、この取り組みを全市的に拡大していきたいと考えております。











